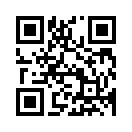2014年06月22日
日本言語学会第148回大会
日本言語学会第148回大会(2014年6月7〜8日,法政大学)に出席しました。
中でも,公開シンポジウム『過去のコミュニケーションを復元する−書き言葉と話し言葉をめぐる三都物語−』という歴史語用論を用いた様々な角度からの発表から様々な知見を得ました。
田中優子氏(法政大学)は文学および言語学の立場から「話し言葉を書く,書き言葉を視る──江戸人たちの言葉の世界」を,
高田博行氏(学習院大学)は「1800年前後のベルリンにおける標準文章語と方言の混交──緩衝材としての「日常語」」において19世紀と16世紀の状況を,
椎名美智氏(法政大学)「「話された書き言葉」と「書かれた話し言葉」――近代英語期ロンドンの言語意識」から夫婦の会話を,
滝浦真人氏(放送大学)が全体のまとめとして「過去のコミュニケーションを詮索する快楽──歴史語用論という箱眼鏡」を発表されました。
その後会場からの質問表に基づき質疑応答がなされ,より詳細な説明がなされました。
ただ,歴史語用論自体の方法論には,聖書本文研究では既になされていることが多いのではと感じましたが,様々な言語やジャンルにおいてなされている研究を見ることができて,触発されました。
中でも,公開シンポジウム『過去のコミュニケーションを復元する−書き言葉と話し言葉をめぐる三都物語−』という歴史語用論を用いた様々な角度からの発表から様々な知見を得ました。
田中優子氏(法政大学)は文学および言語学の立場から「話し言葉を書く,書き言葉を視る──江戸人たちの言葉の世界」を,
高田博行氏(学習院大学)は「1800年前後のベルリンにおける標準文章語と方言の混交──緩衝材としての「日常語」」において19世紀と16世紀の状況を,
椎名美智氏(法政大学)「「話された書き言葉」と「書かれた話し言葉」――近代英語期ロンドンの言語意識」から夫婦の会話を,
滝浦真人氏(放送大学)が全体のまとめとして「過去のコミュニケーションを詮索する快楽──歴史語用論という箱眼鏡」を発表されました。
その後会場からの質問表に基づき質疑応答がなされ,より詳細な説明がなされました。
ただ,歴史語用論自体の方法論には,聖書本文研究では既になされていることが多いのではと感じましたが,様々な言語やジャンルにおいてなされている研究を見ることができて,触発されました。
西アジア言語研究会(12/27,京都産業大学)
夏の語学講座(ヘブル語)(7/29-31,神戸ルーテル神学校)
春の語学講座(ヘブル語)(3/18-20,神戸ルーテル神学校)
平成25年度 西アジア言語研究会(12/22,京都産業大学)
夏のヘブル語語学講座(7/25〜27,神戸ルーテル神学校)
ヘブル語語学講座(7/24〜27,神戸ルーテル神学校)
夏の語学講座(ヘブル語)(7/29-31,神戸ルーテル神学校)
春の語学講座(ヘブル語)(3/18-20,神戸ルーテル神学校)
平成25年度 西アジア言語研究会(12/22,京都産業大学)
夏のヘブル語語学講座(7/25〜27,神戸ルーテル神学校)
ヘブル語語学講座(7/24〜27,神戸ルーテル神学校)
Posted by atake at 23:14
│言語